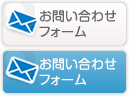HOME>こんなときに>家族・将来のこと>遺言書の作成③ 自筆証書遺言について
遺言書の作成③ 自筆証書遺言について
2012年04月06日
遺言書は公証役場に行かなくても、いつでも、費用をかけずに、自分一人で作成することができます。
ただし、自筆証書遺言を有効にするには次のような法律で定められた方法で作成する必要があります。
1.必ず全部を自筆する必要があります。
パソコン、ワープロで作成することはできません。また、一部でも代筆してもらうことはできません。
2.作成した日付、氏名を必ず書く必要があります。
本人を特定するために、住所、生年月日も記載することをお勧めします。
3.印鑑を押さなければなりません。
4.訂正する方法も決まっています。
間違った場合は、新しい紙に書き直すことをお勧めします。
5.同じ用紙に二人以上の人が遺言を書くことはできません。
夫婦一緒に作成する場合も別々の用紙に書いてください。
遺言書は必ずしも封印しなくてもよいのですが、中を見られたり、後に改ざんを疑われたりしないように、作成したら封筒に入れ、それとわかるように表に「遺言書」と書き、口を閉じて、遺言書と同じ印鑑で封印して 保管する方がよいと思います。
保管する方がよいと思います。
なお、自筆証書遺言の場合は、相続発生後に家庭裁判所で相続人立ち会いのもとで検認という手続きがをする必要があります。保管場所を信頼できる方に知らせておくか、発見されやすい場所に保管することが肝心です。
ただし、自筆証書遺言を有効にするには次のような法律で定められた方法で作成する必要があります。
1.必ず全部を自筆する必要があります。
パソコン、ワープロで作成することはできません。また、一部でも代筆してもらうことはできません。
2.作成した日付、氏名を必ず書く必要があります。
本人を特定するために、住所、生年月日も記載することをお勧めします。
3.印鑑を押さなければなりません。
4.訂正する方法も決まっています。
間違った場合は、新しい紙に書き直すことをお勧めします。
5.同じ用紙に二人以上の人が遺言を書くことはできません。
夫婦一緒に作成する場合も別々の用紙に書いてください。
遺言書は必ずしも封印しなくてもよいのですが、中を見られたり、後に改ざんを疑われたりしないように、作成したら封筒に入れ、それとわかるように表に「遺言書」と書き、口を閉じて、遺言書と同じ印鑑で封印して
 保管する方がよいと思います。
保管する方がよいと思います。なお、自筆証書遺言の場合は、相続発生後に家庭裁判所で相続人立ち会いのもとで検認という手続きがをする必要があります。保管場所を信頼できる方に知らせておくか、発見されやすい場所に保管することが肝心です。